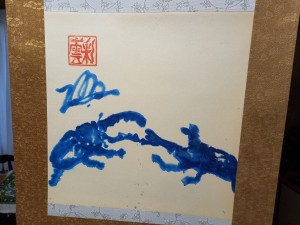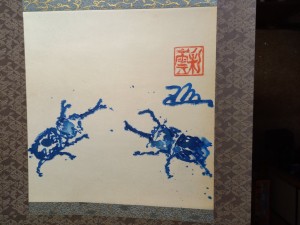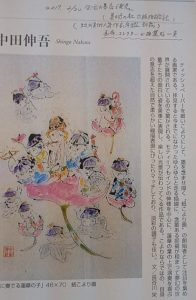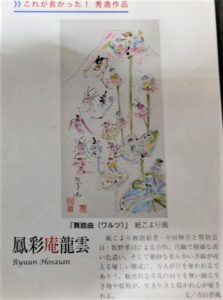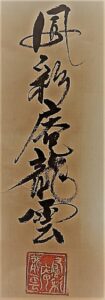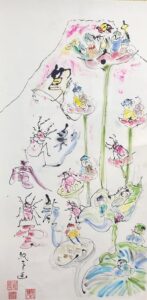グッドルーザー
“グッドルーザー(good loser)”とは、負けっぷりのいい人、「よき敗者」のことをいうそうだ。
明日は開戦記念日である。米国時間では12月7日「THE WAR」だ。
この米国では、米大統領選挙における「敗北宣言」の伝統を、その事例として挙げてある。
恐らく、いまや負けたはずの大統領が結果を認めない事態が続いているアメリカの今後を懸念してのことであろう。このままでは、政権が移行されても民主主義のこうむる痛手は深いと・・・。
長丁場の大統領選は、「民主主義の祭り」の様相を見せるが同時に、皮肉にも祭りのたびに社会は二分された戦いとなる。
ゆえに敗者は勝者を祝福し、勝者は敗者をたたえて、溝を埋める意志を示し合うのが、きれいごとに見えても祭りの終わり方だったという。その良き伝統を壊すような態度を取り続けるトランプ氏の意図はどこにあるのだろうか・・・。
ここまで書いているうちに、「敗軍の将は、兵を語らず」(『史記』)という言葉が頭に浮かんだ。「戦いに敗れた将軍は武勇について語ることはできない。転じて、失敗した者はその事について意見を述べる資格はない」という意味だ。
経営者など組織の上に立つ人たちにとって、“グッドルーザー”の心得は身につけるべき重要な教えだと考える。
“グッドルーザー”を演じることによって、次の二つの効用が期待できる。
一つは、戦いによって生じた分断を「統合」に導くことができる。
負けっぷりの良さが、場の共感を生み出し、差異を認め合う復元力を生み出すことが期待できる。
もう一つは、新たなチャレンジの機会を得ることができる。
「敗れたこと」に対して言い訳をせず、真摯に自己と向き合うことによって、自分自身の慢心さや傲慢さに気づかされて、自己革新の必要性を感じ、新たなチャレンジへの意欲が湧いてくる。
今やパラダイムシフトの時代だ。変革と挑戦をやり続けるなかで、成功と失敗は表裏一体だと思う。いづれにしても、結果から何を学びとるかである。そして、「人間としていかにあるべきか」を見直す機会を怠らないようにしたい。
「祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり。沙羅双樹の花の色、盛者必衰の理をあらはす。奢れる人も久からず、ただ春の夜の夢のごとし」(平家物語)。
(R2.12.07)